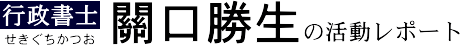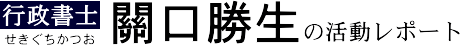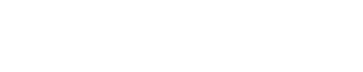あえて遺留分を侵害する遺言を作成する
前回、遺言書の作成を依頼していただいたN田K史さんの実際に作った遺言公正証書の本文は次のようなものです。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
平成28年第○○○号
遺言公正証書
本職は、遺言者N田K史の嘱託により、後記証人の立会をもって次の遺言の趣旨の口述を筆記し、これを証書に作成する。
第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産その他一切の財産を遺言者の妻N田H子(昭和24年2月○日生)に相続させる。
記
①土地
所 在 東京都北区○○町○丁目
地 番 ○○○○番○
地 目 宅地
地 積 68.28平方メートル
②土地
所 在 神奈川県秦野市○○町
地 番 ○○○番○
地 目 雑種地
地 積 76平方メートル
③建物
所 在 東京都北区○○町○丁目○○○○番○
家屋番号 ○○○○番○
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 43.14平方メートル
2階 42.92平方メートル
第2条 万一、遺言者より前に又は遺言者と同時に妻N田H子が死亡していたときは、遺言者は前条記載の財産のうち①及び③並びに③の建物内に存する一切の動産を遺言者の長男N田A彦(昭和49年12月○日)に相続させ、長男N田A彦に相続させるとした財産を除く遺言者の所有する一切の財産(前条記載の②、預貯金、現金その他一切の財産)を次男N田E司(昭和52年10月○日生)に相続させる。この場合、遺言者の一切の債務(遺言者の未払租税公課、入院・治療費、家事債務等)、葬儀費用、遺言の執行に関する費用は長男N田A彦の負担とする。ただし、前条記載②の土地の登記に関する費用は、次男N田E司の負担とする。
第3条 遺言者は、遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべきものとして、妻N田H子を指定する。
2.妻N田H子には、墓地を含む代々の墓及び仏壇など祭祀に必要な財産の一切を相続させる。
3.万一、遺言者より前に又は遺言者と同時に妻N田H子が死亡していたときは、長男N田A彦を遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者とする。
第4条 遺言者は、本遺言の執行者として、妻N田H子を指定する。
2.万一、この遺言の執行完了以前に妻N田H子が死亡、又は執行が不能な状態になったとき、もしくは遺言執行者への就任を辞退したときには、新たな遺言執行者として次の者を指定する。
東京都北区赤羽2丁目2番2-911号
行政書士 關口勝生
昭和47年○月○日生
この場合、遺言執行者に対する報酬は、相続財産評価額の2パーセントとする。ただし、相続財産評価額の2パーセント相当額が金25万円に満たない場合は、遺言執行者に対する報酬は金25万円也とする。
第5条 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。
①不動産、預貯金、株式その他の相続財産の名義変更、解約及び払戻し
②貸金庫の開扉、解約及び内容物の取り出し
③本遺言の執行に必要な場合に代理人及び補助者を選任すること
④その他本遺言を執行するために必要な一切の処分を行うこと
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
付言事項で遺留分を侵害した事情を説明する
この遺言書では、一切の財産を奥様であるH子さんに相続させることにしていますので、明らかに遺留分を侵害しています。
そこで付言事項で、それに至った理由を説明します。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
(付言事項)
1.遺言者(以下「私」と言います)は、妻H子、長男A彦、次男E司とその家族が仲良く幸せな人生を過ごしてくれることを切に願い、この遺言書を作成しました。
2.妻H子には長い間苦労を掛けましたが、いつも明るく私や家族を支えてくれたことに大変感謝しています。H子は立派な家に育ち短大まで卒業しながら、学歴もない一介の職人である私に嫁ぎ、苦労が多かったと思いますが、二人の子を立派に育て上げてくれました。今ある財産は、ひとえにH子の内助の功により築くことができたと思います。したがって、私の財産はすべてH子に相続させることにしました。
長男A彦には、学歴の無い私の子とは思えぬほどの成績で大学まで卒業し、立派な社会人になってくれたことを誇りに思っています。現在、幸せな家庭を築いている様子で何よりですが、私の亡き後は自分の家庭だけでなく、お母さんや弟のことも気にかけてN田家全体が幸せになれるよう努力してくれることを望みます。
次男E司も、優秀な成績で大学を卒業し、立派な社会人となってくれました。また、幸せな家庭を築いている様子を嬉しく思っています。私の亡き後はもう少しお母さんのことを気にかけ、なるべく顔を見せてあげてください。
私の財産をすべてH子に相続させることにしたのは、A彦もE司もそれぞれ家庭を持ち、私亡き後も、H子と同居することは難しいと思われることから、H子が一人ででも平穏な暮らしが送ることができるよう考慮したものであることをご理解ください。
また万一、私より先にH子が亡くなった場合は、自宅をA彦に相続させることとしていますが、これはA彦には長男としてN田家をまとめていってもらいたいという思いからです。その他の財産はE司に相続させることにしたものの、兄弟で不均衡になってしまったことは否めません。ですが、どうぞご理解をいただき、兄弟仲良く助け合っていって下さい。
3.以上のような思いから熟慮に熟慮を重ね、この遺言書を作りました。遺留分を侵害する内容になっているかと思いますが、どうか減殺請求などせずに遺言書のとおり相続していただきたいと願っています。
4.みんな、今までありがとう。これからも仲良く幸せに過ごしてください。
以上
本旨外要件
東京都北区○○町○丁目○○番○号
無 職
遺言者 N田K史
昭和19年1月○日生
遺言者は、印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
東京都練馬区○○町○丁目○番○-○○○号
会社員
証 人 N田K祐
昭和49年9月○日生
東京都北区赤羽2丁目2番2-911号
行政書士
証 人 關口勝生
昭和47年2月○日生
上記各事項を列席者に読み聞かせたところ、各自、筆記の正確なことを承認し、次に署名押印する。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
付言事項でストレートに思いを伝える
遺言者のN田K史さんは、もともと財産はすべて奥様に残すとお子さん二人に言っていますし、奥様のH子さんが財産をすべて相続しても、H子さんが亡くなったときには、その財産はお子さん二人が相続するわけですから、仮に遺言書が無かったとしてもH子さんがすべて相続することになったかもしれません。
ただ、お子さんのA彦さんにもE司さんにも家庭があり子供がいるとなると、学費などで物入りになり、K史さんの財産をあてにしているということも考えられるわけです。その時すんなりH子さんがすべての財産を相続できるかどうかという不安もあります。
その不安を解消するためにこのような遺言書を作り、さらに付言事項でストレートに思いを伝えることで、「お父さんの言う通りにしようかな」という気にさせて、遺留分があっても請求しないような気持に持っていくわけです。
また、もし妻のH子さんのほうが先に亡くなってしまった場合は、兄弟間で不均衡が生じてしまいました。
自宅以外の財産がもっとあれば、もっと上手い配分ができたかもしれませんが、現在の財産状況とK史さんの意向を考慮して、この形にしてあります。
遺言執行者については、全財産を妻のH子さんに渡す内容になっていますのでそれほど難しい処理があるわけでなく、H子さんがかなりしっかりした方なので、わからないことがあった時はうちの事務所に相談をしてもらうということで、H子さんに執行者になってもらうことにし、H子さんが就任できない場合に私が就任するようにしてあります。
※この記事は、実際にあった事例をもとにしたフィクションです。したがって公正証書の文例も実際の公正証書の文面を、記事用に修正したものです。
遺言書のご相談はお気軽に!
關口行政書士事務所
〒115-0045
東京都北区赤羽2-2-2赤羽スカイハイツ911
【TEL・FAX】03-3903-2888
HP: http://www.sekiguchikatsuo.com
付言事項で遺留分の壁を乗り越える② 遺留分 遺言
Tweet